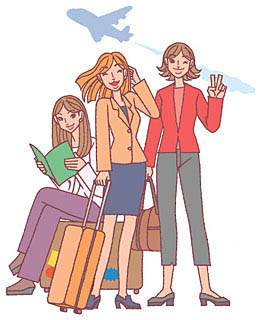お歳暮は、日頃お世話になっている方々へ感謝の気持ちを込めてお礼の品を贈るものです。
なので、お祝いごとではありません。
でも、もしも自分や相手方に不幸があって喪中の場合、注意しないといけないことがあります。
そこで今回は、お歳暮を自分が喪中の場合に贈る時と頂いた時のマナー、相手が喪中の場合にお歳暮を贈る時のマナーなどについて紹介していきましょう。
お歳暮を自分が喪中のときに贈る場合のマナーとは?
自分の方が喪中の場合、お歳暮を贈る時に気をつけないといけないことを紹介していきますね。
お歳暮は喪中であっても贈っても構いません。
こちらが落ち着いていないこともありますが、反対に相手に気を遣わせてしまう場合もあります。
また、中には喪が明けていない方に贈り物をされることをよく思われない方もいらっしゃいます。
なので、四十九日を迎えていない場合は、法要も終わって心も落ち着いてからお歳暮は贈るようにしましょう。
お歳暮を贈る時、普通は紅白の水引が使いますが、喪中の場合、紅白は望ましくありません。
喪中の場合は、無地の奉書紙、または無地の短冊を使うのがマナーです。
その際、表書きにはお歳暮と書いても構いません。
お歳暮を自分が喪中のときに頂いた場合のマナーとは?
もしも自分の方が喪中の時にお歳暮が贈られてきた場合、受け取っても問題はありません。
お礼状は、いただいてから3日以内に出すのがマナーです。
また、お歳暮のお返しは基本的には必要はないのですが、お返しをしたい場合もあるかもしれません。
お返しを贈る場合は、「お歳暮」として贈っても問題はありません。
しかし、少し気が引けるようなら松の内を過ぎてから、「寒中御伺」や「寒中御見舞」として贈るといいでしょう。
お歳暮を相手が喪中のときに贈る場合のマナーとは?
毎年お歳暮を贈っている方が喪中の場合、本当に贈ってもいいのかな?と不安になりますよね。
でも、相手方が喪中の場合でも、いつも通りお歳暮を贈っても構いません。
その場合は、お歳暮を贈るのは控えましょう。
相手方のことを考えると、四十九日の法要が終わってから贈るのが無難です。
なので、四十九日が終わってから「寒中御見舞」として贈るようにしましょう。
せっかく感謝の気持ちを込めてお歳暮を贈るのに、相手を不快な気持ちにさせてしまっては元もこうもありません。
一番大事なのは相手のことを考え、気配りを忘れないようにすることがマナーです。
まとめ
お歳暮はお互いが喪中であっても、お祝いごとではありませんので、いつも通り変わらず贈っても大丈夫です。
でも、喪中ということで避けた方がいい事柄がいくつかあります。
それを間違うと、せっかくの気持ちが相手に不快な思いをさせてしまうという残念なことになりかねません。
喪中の場合にお歳暮を贈る時は、お互い四十九日の法要を終えて、落ち着いてからというのがマナーだと思っておきましょう。
引き続き今後も良い関係でお付き合いしていくためにも、相手のことを一番に考えるようにしましょう。
>> お歳暮のハムはなぜ定番なの?賞味期限や保存方法、美味しい食べ方は?
>> お歳暮は何を贈る?人気商品やカタログギフト、お礼状の書き方とは?