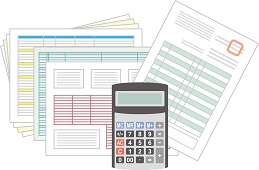3月3日の桃の節句といえば、女の子が喜ぶ雛人形ですよね。
私が子どもの頃は、大きな部屋がある家ではありませんでしたので、ケース入りの雛人形を飾ってもらっていました。
なので、広い和室で7段飾りの雛人形を飾ってもらっているお家が羨ましかったです。
そこで今回は、雛人形はいつからいつまで飾るものなのか、初節句の雛人形はいつ買うのか、処分の仕方などについて紹介したいと思います。
雛人形はいつからいつまで飾るの?
雛人形を飾る時期ですが、いつからいつまで飾るのか気にする方も多いと思います。
なぜなら、ひな人形をしまう時期が遅れてしまうとか、婚期も遅れるなんて言われていますからね。
まず、飾る時期ですが、立春(2月4日)~2月中旬にかけてが良いと昔から言われています。
節分で厄を払った後に飾る と覚えておいたら良いですよ。
飾り付ける時期については、特に決まっているわけではありません。
ただし、最低限、雛祭りの一週間前までには飾り付けを終わらせておいた方が良いでしょう。
そして、雛人形は大安日に出すのが縁起がいいと言われています。
でも、一番いいとされているのは、啓蟄の日(けいちつのひ)だと言われています。
啓蟄の日は二十四節気の中のひとつで、日にちとしては3月5日または6日です。
ちなみに、2016年と2017年の啓蟄の日は3月5日で、2018年と2019年が3月6日になっています。
なお、片付ける日は晴れた乾燥した日にした方が雛人形にカビなど付かなくて良いですよ。
雛人形の飾り方と片付け方の様子
初節句の雛人形はいつ頃買ったらいいの?
特に、1月~2月に生まれた赤ちゃんの場合、初節句はどうしたらいいのか悩みますよね。
生まれてすぐに初節句がやってくるわけですが、お祝い事をするにはまだ小さすぎます。
そんな場合は、生まれた翌年に初節句をする ようにしましょう。
例えば、赤ちゃんが生まれて21日以内に節句を迎える場合、その翌年に初節句を行うというような考え方が多いようです。
雛祭りの間際になって慌てて買いに行っても、目ぼしい雛人形は残っていない可能性があります。
また、年が明けると雛人形を買いに行かれる方が多くなり、売場も混雑しています。
そういう意味でも、1月~2月に生まれ、そこから買いに行くというのは大変なんです。
なので、翌年に余裕を持って雛人形を選び、お祝いしてあげる方がいいと思いますよ。
雛人形は何歳まで飾るの?処分の仕方はどうする?

雛人形って、自分が何歳ぐらいの頃まで飾っていたのか覚えていらっしゃいますか?
たぶん、多くの方が気がついたらなくなっていたように思うのですが、私もどうやって処分されたのか覚えていません。
でも、私が小学生の頃までは飾っていたと記憶しています。
そこで、両親や親戚、友人などを含めて、色んな方に雛人形の処分の仕方を聞いてきました。
雛人形は女の子にとってお守りのような存在でもありますから、今までありがとうという感謝の気持ちを込めてお別れするようにしましょう。
雛人形の処分方法のひとつとしては、人形供養を代行してくれる日本人形協会があります。
毎年10月頃に東京の明治神宮で行われる「人形感謝祭」で供養してくれます。
また、人形感謝(供養)代行サービスというのがあって、ネットで申し込んだ後に梱包しておくだけで、郵便局が自宅まで取りに来てくれるそうですよ。
なお、近所のお寺や神社で供養してくれるかどうか、一度問い合わせてみてもいいと思います。
なので、何歳まで飾るものという明確な決まりはなく、何歳になっても飾るものとも言われています。
結婚するまで飾るという方も結構多かったのにはびっくりしました。
ちなみに、私の雛人形は、まだ処分されていなくて、押入の奥に大事にしまってあると両親に聞きました。
いつかは処分しなくてはと思ってたそうですが、変な処分の仕方をして娘が不幸になってはと思い、ずっとそのままにしてたそうです。
私の家庭のように処分しないで保存しておくのも一つの方法だと思いますが、娘の結婚をひとつの区切りに処分するのも有りかもしれませんね。
まとめ
実際に雛人形を片付けるのが遅くなってしまったとしても、婚期が遅れるというのは迷信のようですね。
でも、ずっとそう言われてきたのは、片付けができないようでは、きちんとしたことができるお嫁さんにもなれませんよ、というしつけの意味が込められているそうです。
雛人形について、自分が子どもの頃は両親がすべてしてくれていたので、自分が親になると意外に知らないということが多い方もたくさんおられるのではないでしょうか。
面倒だと感じることもあるかもしれませんが、ひな人形は女の子の健康と幸せを願いつつ、大切にしてあげてほしいなと思います。
娘さんの幸せを願っています。