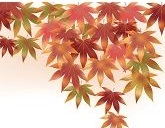節分と言えば、「鬼は外、福は内」の豆まきと、もう一つお馴染みの恵方巻きですよね。
最近では、サラダ巻きなどの太巻きとして食べることもあります。
また、コンビニでは、丸かぶりロールなんていう甘いロールケーキが売り出されていますね。
でも、なんで節分に恵方巻きを食べるのかとか、毎年の方角ってどうやって決まるの?って疑問に思う方も多いと思います。
そこで今回は、恵方巻きの由来や方角の決め方、食べ方と関西と関東の違いなどについて紹介しましょう。
恵方巻きの由来と方角の決め方とは?
そもそも、恵方巻きの由来とは、江戸時代から明治時代にかけて、大阪の花街で節分をお祝したり、商売繁盛を祈願して始まったそうです。
つまり、発祥は大阪 なんですね。
花街で芸人や芸子たちが節分に芸遊びをしながら、恵方巻きを食べたと言われています。
その当時は、「丸かぶり寿司」や「太巻き寿司」と呼ばれていました。
それが、大手コンビニエンスチェーンが太巻きを売り出すようになり、その際に「恵方巻き」という名前がつけられたという説があります。
今では全国的に広まっていますよね。
恵方巻きは、その年によって食べる方角があります。
2016年の方角は、南南東 です。

ところで、恵方巻きの方角ってどうやって決まるのかご存知ですか?
縁起の良い方角のことを恵方と呼ばれることはご存知ですよね。
歳福神、その歳の福徳を司る神様がいらっしゃる方位に向かって、願い事をしながら食べます。
恵方巻きの方角は、西暦の下一桁によって決められているんです。
5と0の年(2015年)は、西南西より少し西
6と1の年(2016年)は、南南東より少し南
7と2の年(2017年)は、北北西より少し北
8と3の年(2018年)は、南南東より少し南
ただし、恵方と呼ばれる方角は4つしかありません。
恵方巻きの4つの方角
この4つの恵方の方角を、東 ⇒ 西 ⇒ 南 ⇒ 北 ⇒ 南という順に、5年周期で繰り返しています。。
したがって、5年後の2021年の恵方の方角は、今年2016年の恵方と同じ南南東になるということです。
ドラえもんの恵方巻き 2016
恵方巻きの食べ方と食べる理由について
恵方巻きの食べ方は、恵方の方角に向かって、1本を切らずに丸ごと、願い事をしながら無言で食べます。
また、神社などでお祈りする時に、しゃべらず無言ですることから来ているとも言われています。

でも、1本切らずにかぶりつき、無言で食べるというは、正直結構つらいものがありますよね。
それに、太巻きだとそんなに大きく口を開けれないので、切って食べたい衝動にかられます。
でも、「縁」は切らず大切にしたいですから、恵方巻きに込められた理由を頭に入れて、頑張って食べるようにしましょうね。
恵方巻きと太巻きの違いと呼び方の違いとは?
恵方巻きと太巻きの違いってご存じですか?
私も、節分に食べる太巻きのことを、ただ単に恵方巻きと言うのでは?と思っていました。
しかし、中に入っている具に違いがありました。
恵方巻きの具材は、七福神に似せた7種類の具が入っている太巻きなんですね。
また、恵方巻きは関西と関東で呼び方に違いがあります。
私は関西の人間ですので、海苔で巻いたお寿司のことを「巻き寿司」と呼びます。
関西では太さに関係なく、巻き寿司と言うことが多いです。
そして、使う海苔も焼きのりではなく、乾燥させただけの乾海苔を使います。
一方の関東では、「海苔巻き」と呼ぶそうです。
太さによって、細巻き、中巻き、太巻きなどと分けて呼んでいますね。
使う海苔も、パリッとした感触があるということで、焼き海苔を使うそうですよ。
まとめ
今までは恵方巻きの事は何となく知っている程度で、いつもスーパーで売っている太巻きを食べていました。
そして、方角についてもそんなに意識した事はありませんでした。
最近では節分時期になると、恵方巻きにちなんだ色んな太巻きが売り出されますよね。
いろいろ恵方巻きも進化していっているのか、はたまた、コンビニやスーパーの思惑に引っかかっているのか疑問に感じる時があります。
でも、いろいろ調べて行くと、中に入っている具材にまで意味があります。
なので、節分には本来の太巻き寿司を食べながら、福を巻き込んでいきたいですね。