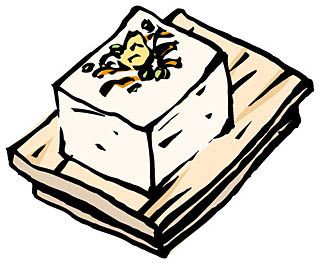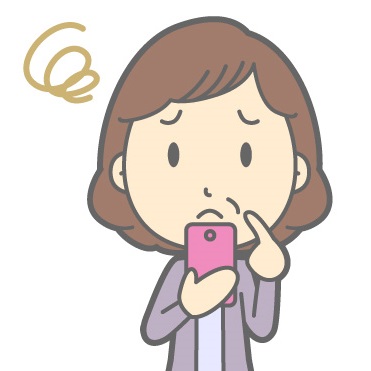自営業の人はともかく、一般的に会社勤めをしてきた人や、公務員であった人などは、これまで確定申告には、あまり縁がない人が多いものだと思います。
基本的に会社員や公務員であれば、会社が必然的に年末調整を行ってくれました。
なので、自身で確定申告が必要な場合は、住宅ローンの控除を受けるためぐらいのものでしょう。
では、定年退職後の確定申告が必要な人と、確定申告の仕方や方法について、詳しく紹介していきたいと思います。
定年退職後の確定申告が必要な人とは?

定年退職後の確定申告が必要な人は、実はほとんどすべての人が対象になります。
何故なら、退職した年に限りは、所得税の精算が済んでいないため、確定申告が必要になるからです。
そのため、ほぼ全ての人が定年退職後の確定申告が必要な人といえますが、2年目以降はどうなるのか見ていきたいと思います。
2年目以降で定年退職後の確定申告が必要な人は、大きく2つの条件があります。
要するに、収入が多くある人です。
定年退職前は、年収で400万円といえば一般的なものであり、400万円を超えて収入を得ている人も多かったと思います。
また、公的年金の平均的な受給額は、250万円ぐらいから300万円ほどと言われていますので、なかなか年金受給者で400万円を超える人は少ないと考えられます。
少し分かりにくい表現ですが、分かりやすく給与収入で計算すると、だいたい85万円を超える場合は、所得金額が20万円を超えることになります。
定年退職後も、がっつり働こうと思っている人は、所得金額が超える人も多いかもしれませんね。
また、その他にも様々な控除を受けたい場合には、確定申告をする必要があります。
医療費控除の詳細は省略しますが、一年間で10万円以上の医療費を支払っていれば、確定申告を行うことで、一部の金額が戻ってくる場合があります。
定年退職後の確定申告の仕方や方法について

定年退職後の確定申告の仕方について、どうすればいいのか不安に感じている人も多いかもしれません。
今まで確定申告など、ほとんどせずに過ごしてきた人が多いと思うので、当然と言えば当然の悩みでしょう。
そこで、定年退職後の確定申告の仕方について、まとめていきたいと思います。
定年退職後の確定申告の仕方については、まずは確定申告の時期を知っておく必要があります。
確定申告の時期は、基本的には2月16日から3月15日の間にすることになっています。
この期間の間に、前年度1年分の会計の結果について、税務署へ確定申告することになっています。
確定申告の仕方は、大きくわけて3つあります。
まず一つ目が、管轄の税務署に行き、直接確定申告を行う方法です。
初めてであり、不安がある方については、間違いなくこの方法をお勧めします。
なぜなら税務署に行けば、税務署の職員が親切丁寧に確定申告の書類の書き方を教えてくれるからです。
必要な書類さえ持参をすれば、混み合うため時間はかかるものの、間違いなく確定申告が意外と簡単にできるはずです。
2つ目の方法は、管轄の税務署に確定申告書を郵送する方法で、3つ目の方法がインターネットで済ます方法です。
インターネットで済ます方法は「e-Tax」とも呼ばれていますが、どちらも間違いがあれば、再度修正をする必要があります。
いずれも、慣れている人にはお勧めですが、初めての人には少し難しいと思います。
まとめ
定年退職後の確定申告について、まずは、する必要があるのか、必要がないのかを知ることから始まります。
医療費などの控除も受けられるため、知らずに損をする場合もあるので、しっかり調べておくことが大事です。
また、初めての確定申告で不安がある方は、間違いなく直接税務署に持参することをお勧めします。
分からないことは専門家に聞くことで簡単に解決しますので、安心して税務署に出向き、間違いのない確定申告を行いましょう。