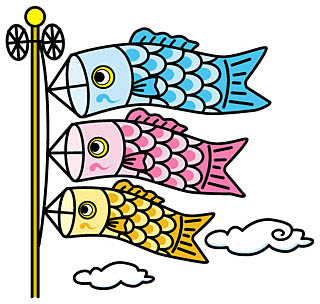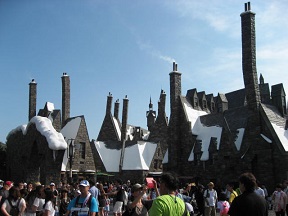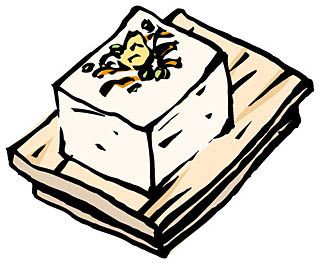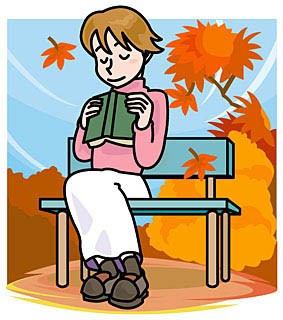起立性調節障害という病気を最近よく聞くことがありますよね。
血圧が低くなりすぎて、起きたくても体がいうことを利かなくなり朝起きられないようになる病気です。
日本ではまだ知名度が低いため、中々理解されにくいのが現状なんです。
そこで今回は、起立性調節障害で朝起きられない子どものために原因と治療方法などについてご紹介しましょう。
起立性調節障害の原因と治療方法は?

普通の人は、寝ている姿勢から立ち上がる際は、一瞬だけ血圧が下がり、その後はすぐに血圧が自然と上昇してくるので体を動かすことができます。
しかし、起立性調節障害になると、この血圧の上昇がうまくいかなくことから、起立性低血圧症とも呼ばれています。
起立性調節障害の原因とは?
起立性調節障害の原因としては、下記のことが考えられます。
運動不足になると筋力が低下しますから、それにともなって低体温になりやすくなります。
また、全身に血液を送るポンプの役目のある筋力の低下で、血圧を上昇させる力も弱くなります。
強いストレスがあると、気力も失われ体の活力が低下するため血圧が上がりにくくなります。
甘い食べ物や飲み物を摂り過ぎると脱力感が強くなり、活力も低下して血圧が上がりにくくなります。
このような原因がある場合、体温も低くなる傾向にありますから、できるだけ運動や食事、睡眠、入浴などの生活習慣を見直して体温を上げるための努力が必要です。
起立性調節障害の治療方法とは?
起立性調節障害の治療方法としては、下記のことが有効だと言われています。
まずは乱れがちな起床時間や就寝時間、食事と入浴の時間などの生活リズムが一定になるように整えましょう。
特に起床時間や就寝時間が不規則だと、交感神経と副交感神経を切り替える自律神経の機能がうまく働かないため目覚めや寝付きが悪くなり、体の疲れが取れません。
体が疲れてダルい状態だと、朝起き上がろうとしても起きられなくなります。
そこで生活リズムが一定になるように整えると、交感神経と副交感神経との切り替えもスムーズになり、疲れもなく朝起きられるようになります。
自律神経の機能がうまく働かない状態だと、手足や脳の末端にまで十分に血流が行き渡らなくなります。
そうなると体が冷えて、ますます血の巡りが悪くなります。
体を温めるには、玉ねぎや大根、ニンジン、かぼちゃなどの根菜類や大豆などの豆類、クルミやピーナッツ、アーモンドなどのナッツ類を積極的に摂るようにしましょう。
筋力が衰えると血の巡りが悪くなります。
特に脚のふくらはぎや太ももなどの大きな筋肉には、血液を心臓や全身に巡らすポンプ作用があります。
その脚の筋肉が衰えると血液を十分に送れなくなるばかりか、最悪は脳貧血などの症状を引き起こしてしまいます。
脚のふくらはぎや太ももなどの大きな筋力の低下を防ぐには、ウオーキングやジョギングなどの有酸素運動が効率的です。
このように普段の生活習慣や生活リズムを見直す治療法が起立性調節障害には有効です。
ただし、最初からいきなり全部やろうとすると、それもまたストレスになって逆効果になりかねません。
普通の目覚まし時計だと、寝ている途中でアラームが大音量で鳴り響くと寝覚めも悪いし、びっくりして心臓にも悪いですよね。
朝起きられなくて、学校に行けない、会社に行けないなどで悩んでいるのなら、光目覚ましをためしてみるのも良いかも知れませんね。
まとめ
起立性調節障害という病気はまだ認知度がそんなに高くはありません。
そのため、起立性調節障害になった子どもや大人は、単に怠け者とか仮病だと言われ、ストレスが悪化することが多いようです。
特に子どもが朝起きられずに学校に遅刻したり、休むようになると親の方もどうしたら良いのか不安になるものです。
もしも起立性調節障害の症状があるようなら、強く怒ったりする前に、一度小児科で診てもらうことも大切ですよ。