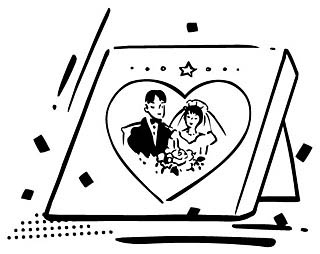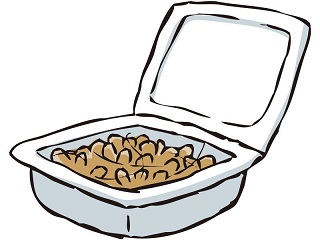身内に不幸ごとがあった時に、年賀状がだせなくなったことを知らせるのが喪中ハガキですよね。
みなさんは喪中ハガキをいつから出すか、いつまでに出すかご存知でしょうか。
意外に知らない人も多いのかも知れません。
そこで今回は、喪中ハガキはいつから出すのか、いつまでに出すのか、文面や続柄、日付の書き方について紹介していきたいと思います。
喪中ハガキはいつから出す?いつまでに出すのが正解?

喪中ハガキはいつから出すか、喪中はがきはいつまでに出すものか、ご存知でしょうか。
喪中ハガキは、年中に身内の不幸があった時に、年賀状を出すことが出来なくなった旨を知人や友人などに知らせるものです。
ただし、喪中ハガキはいつから出すのかについては、特に決まりはありません。
ですが、喪中はがきはいつまでに出すものかについても、相手が年賀状を書く前までがマナーとなります。
とは言うものの、あまりに早く出し過ぎるものでもありません。
例えば夏ぐらいに届いたら、相手も驚き、せっかちな人だと思うことでしょう。
準備が早い人もいるでしょうから、可能であれば11月中に届くように送ることができれば最高だと思います。
これは、あってほしくないことですが、年の瀬に不幸があった場合は、年明けでも構いません。
喪中ハガキをいつから出すのか、喪中はがきはいつまでに出すものか、これでもう大丈夫ですね。
年賀状の準備を始める前、11月下旬から遅くても12月上旬には届くように送るようにしましょう。
喪中はがきの文面|続柄や日付の書き方について

喪中はがきの文面の続柄や日付の書き方はご存知でしょうか。
喪中はがきを書き慣れている人のほうが少ないと思いますので、喪中はがきの文面の続柄や、喪中はがきの文面の日付の書き方について、文例なども紹介します。
もちろん、「家内」や「主人」でも大丈夫です。
最後に、例文を一つ紹介します。
平成〇年〇月 父〇〇が七五歳にて永眠いたしました
永年にわたるご厚情に心から御礼を申し上げます
なお時節柄一層のご自愛の程お祈り申しあげます
平成〇年〇月 差出人住所 差出人氏名
まとめ
喪中ハガキをいつから出すのか、喪中はがきをいつまでに出すのかについては、11月下旬から遅くとも12月上旬に相手に届くように出しましょう。
年の瀬に不幸があった場合は、年明けの「寒中見舞い」で問題ないです。
喪中はがきの文面について、続柄の書き方や日付の書き方も大丈夫ですね。
夫の父、夫の母が亡くなった時のみ「義父」、「義母」ではなく「父」、「母」になるので気を付けてください。
日付も正確な日時ではなく、「本年〇月」、「平成〇年〇月」という書き方が慣例です。