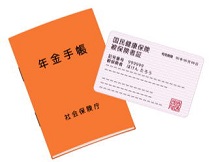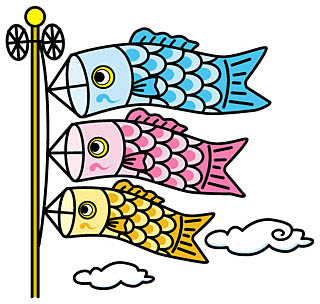自然災害はいつ何が起こる分からないという怖さがあります。
ですから、事前に知識だけは知っておき、いざという時は冷静に対処することが求められます。
さて、高波の基準はご存知でしょうか。
また、高潮との違いや津波との違いは知っていますでしょうか。
よく聞く言葉、みなさん知っている言葉だとは思いますが、正しく理解されているという人は案外少ないのではないかと思います。
そこで今回は、高潮と津波が同時にくることはあるのかということについても気になる人も多いかと思いますので、まとめていきたいと思います。
高波の基準は?高潮との違いは知ってる?

高波の基準は実はないということを知っている人は少ないのでないでしょうか。
高潮との違いは後程説明しますが、まずは高波の基準について詳しく見ていきます。
言葉の意味を説明しますと、強い風が原因で起きる被害をもたらす波のことを高波と言います。
そして、それが高くなればなるにつれ災害のリスクは高まり、気象庁も注意報、警報とレベルを上げていきます。
おおよその目安で言いますと、日本海や太平洋などの外海5メートルから6メートル以上、東京湾などの内海では3メートルから4メートル以上だと言われています。
次に高潮との違いについて、詳しくみていきたいと思いますが、まず言葉を定義しますと、台風や低気圧が原因で起こる海面の上昇のことを高潮と言います。
別名では風津波とも言われることがあるそうで、怖いのは水位が高まりすぎて陸地に侵入をすることです。
また満潮やうねりの周期と一致してしまうと、さらに水位が高まって、危険のリスクも高まります。
高波の基準は具体的な数値はありませんので、天気予報を見て波浪注意報や波浪警報が出ていたら警戒を怠らないように注意してください。
高潮との違いはおさえられたと思いますが、どちらも怖い災害には違いはありませんのでご注意くださいね。
高潮と津波の違いは?同時に来ることはあるの?

高潮については先ほど、海面の上昇が台風や低気圧が原因で起こるものだと説明をしました。
では津波との違いを早速見ていきたいと思います。
この言葉の方がみなさん馴染みがあり、地震と同時に発生するものというイメージをなんとなくお持ちかと思いますが、ずばり高潮と津波の違いは、原因となる自然現象で、みなさんのイメージどおり、地震が原因で生じる大規模な波の伝播現象のことを言います。
また滅多にないことではりますが、ごくまれに隕石の衝突が原因となる場合もあるようです。
そして、それらが同時に起こる可能性は専門家の話を聞く限りでは、極めて小さい可能性ではありますが、可能性としてはゼロではないようです。
私自身も研究者の論文を読みましたが、具体的な数値については記載はありませんでしたが、可能性としてゼロではなく、万が一同時に発生した場合はやはり甚大な被害にいたる可能性があるとのことでした。
高潮と津波の違いは理解できても、同時にくる可能性がゼロではないことが分かっても、やはりいつ何が起こるかわからないのが災害の怖さだと思います。
海沿いに面した地域にお住まいのかたは、知識を知っておくことももちろん重要ですが、いざという時にどこに逃げるかということをしっかり確認しておくことも大事なことだと私は思います。
まとめ
復習になりますが、高波の基準は各地でことなるため、明確なものはありません。
高潮との違いは風が原因か気圧が原因の違いということもご理解いただけたかと思います。
さらに津波との違いですが、海岸や海底の地形が急激に変わることで発生する波の伝播現象になりますので、原因は自身や火山活動などが考えられます。
また高潮と津波が同時に発生する確率は残念ながらゼロではないということが専門家の見立てになります。
知識を身に着けるのが最初の一歩、二歩目は起きた時にどうするかを考えることだと思いますので、次の一歩を考えておくことも大変重要なことだと思います。